 アート
アート セーラちゃん館長「まぼろし博覧会」@伊東市を探訪!「キモ可愛い楽園」を体験した
 アート
アート デザイン
デザイン アート
アート 映画
映画 アートとデザイン
アートとデザイン デザイン
デザイン アートとデザイン
アートとデザイン アート
アート アート
アート アートとデザイン
アートとデザイン アートとデザイン
アートとデザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン アートとデザイン
アートとデザイン デザイン
デザイン 旅
旅 旅
旅 デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン アート
アート デザイン
デザイン アート
アート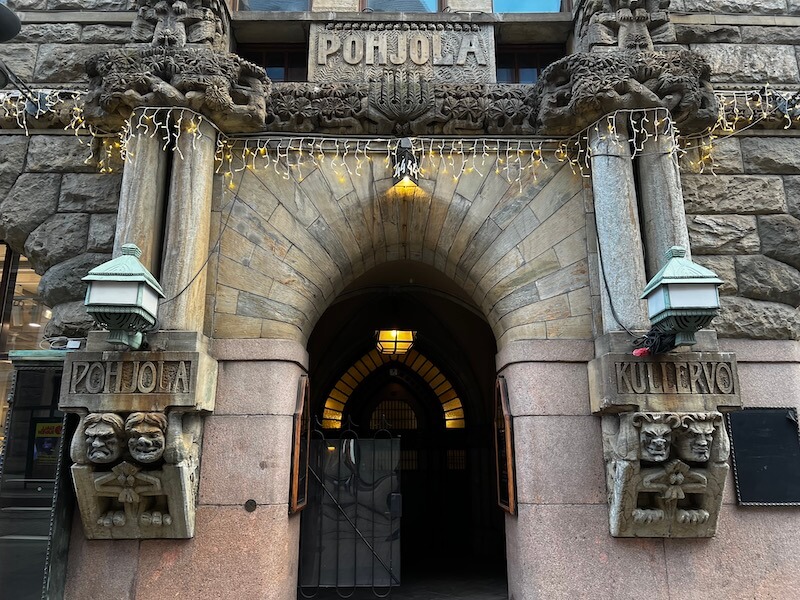 デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン アート
アート デザイン
デザイン アート
アート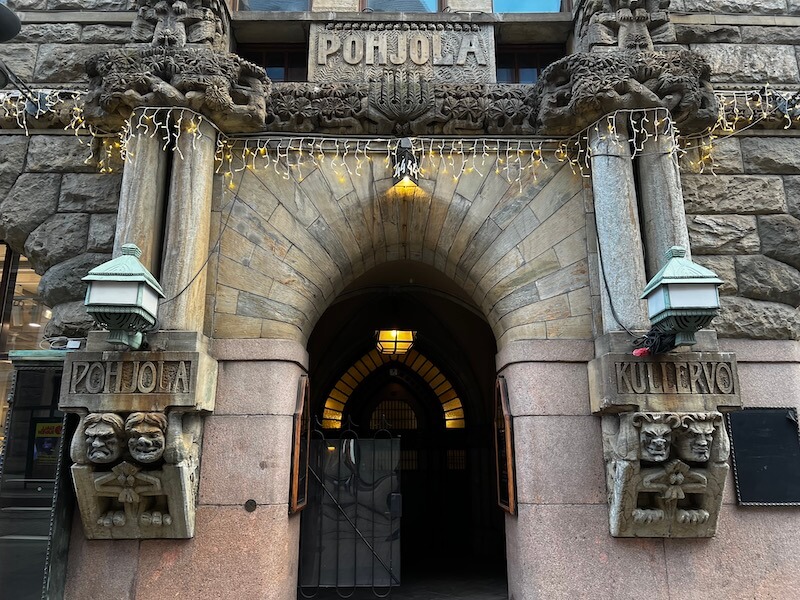 デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン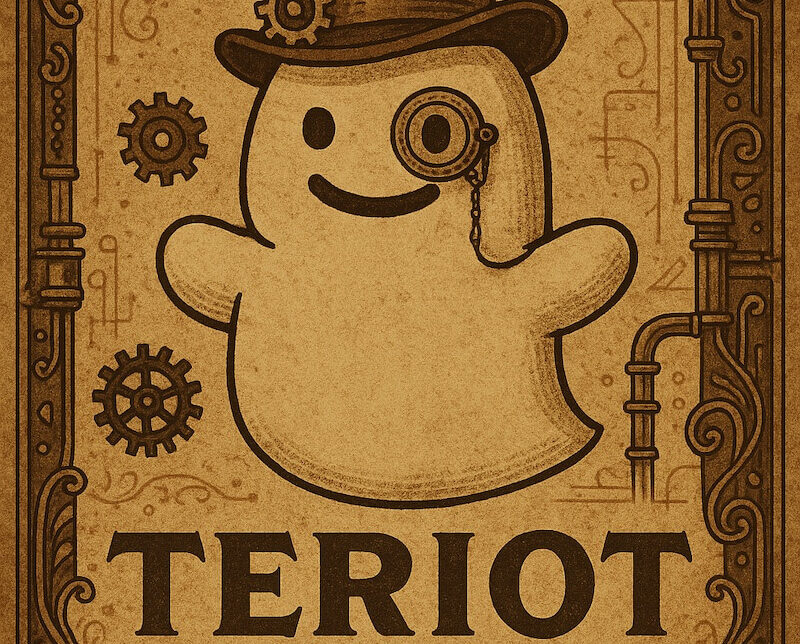 アートとデザイン
アートとデザイン 旅
旅 旅
旅 デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン デザイン
デザイン アート
アート デザイン
デザイン アート
アート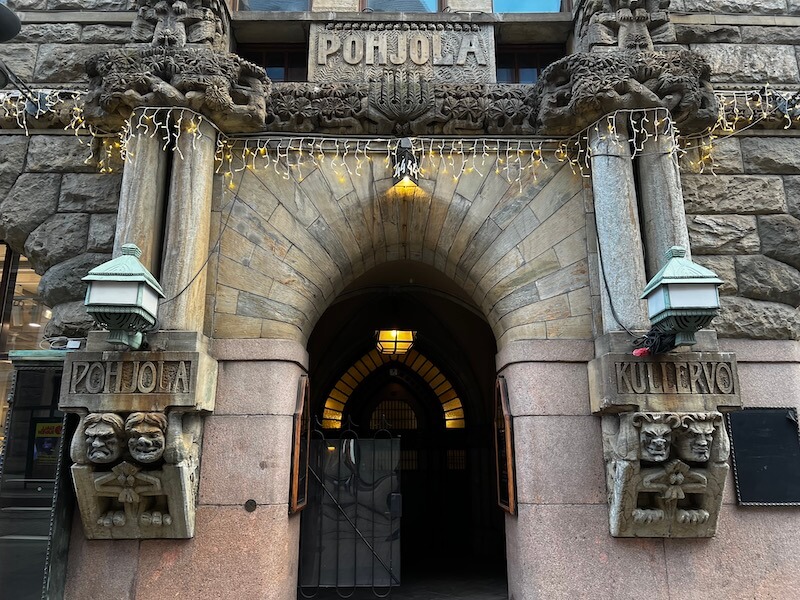 デザイン
デザイン デザイン
デザイン アート
アート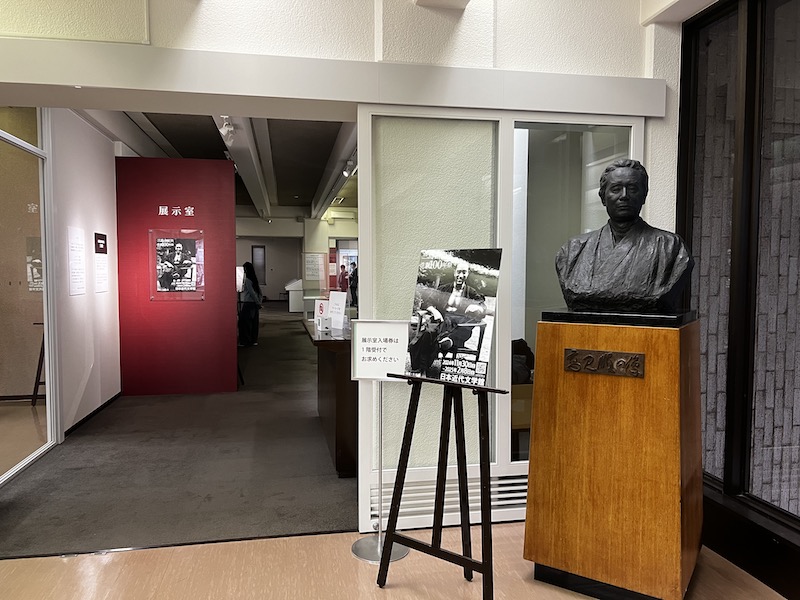 文学
文学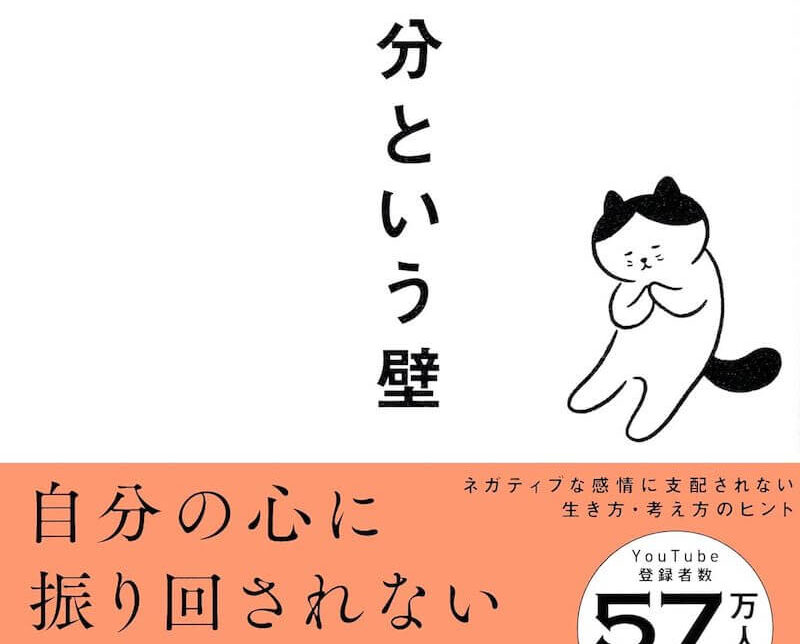 本と映画
本と映画 アートとデザイン
アートとデザイン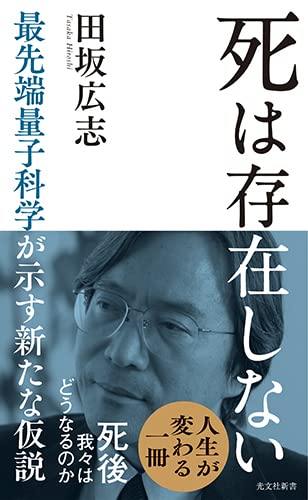 本と映画
本と映画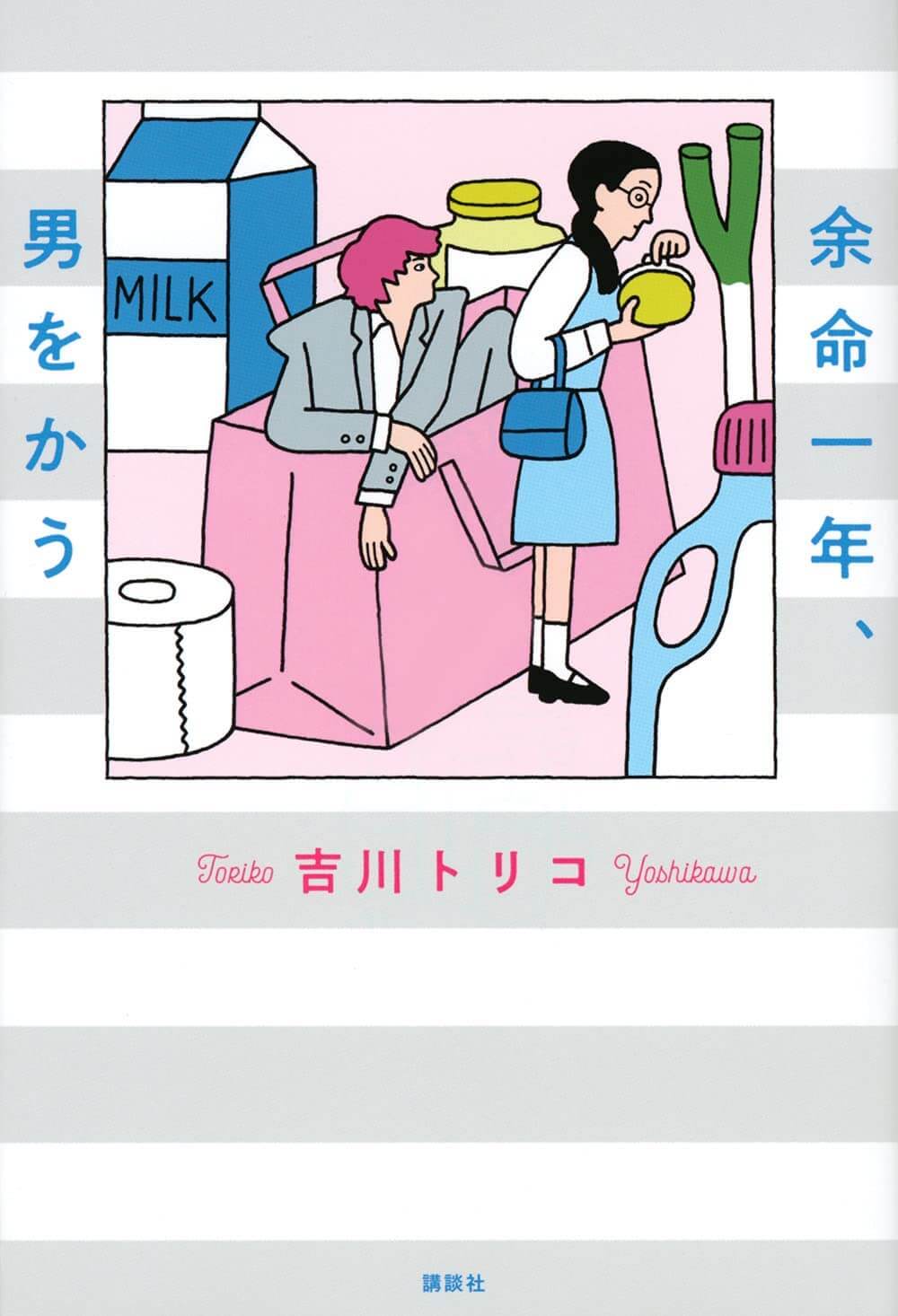 文学
文学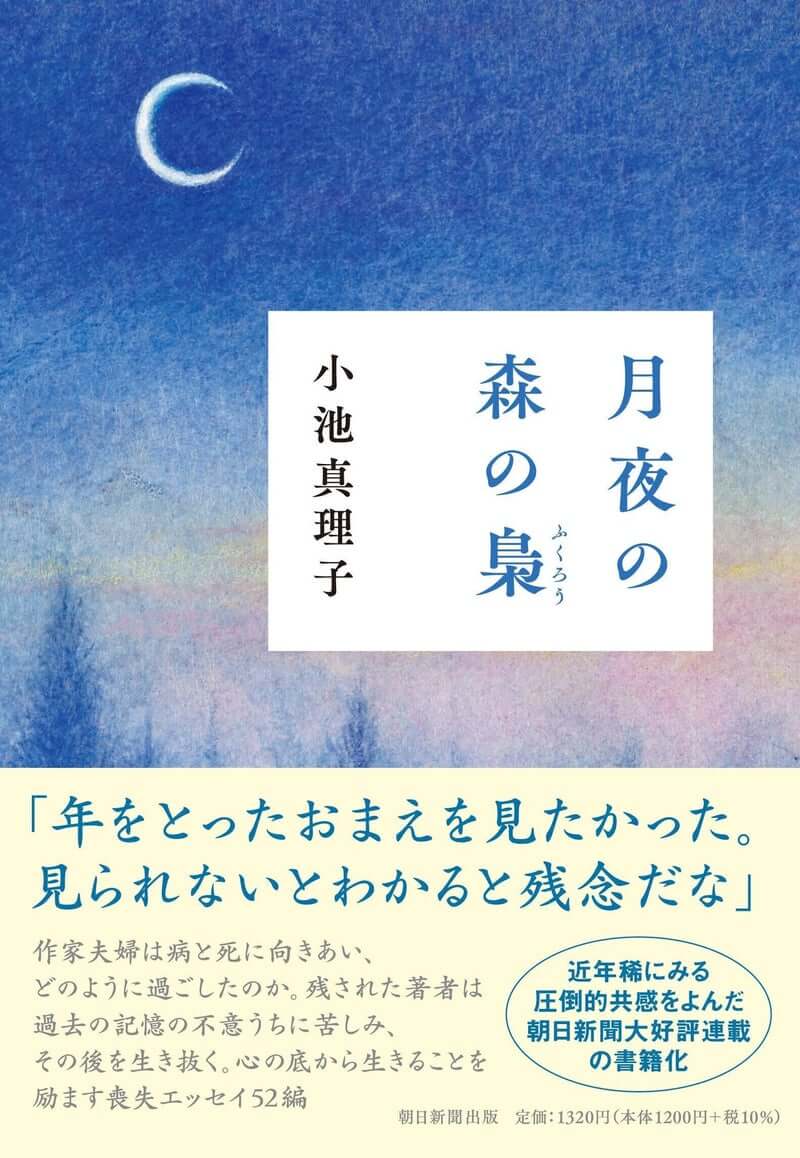 文学
文学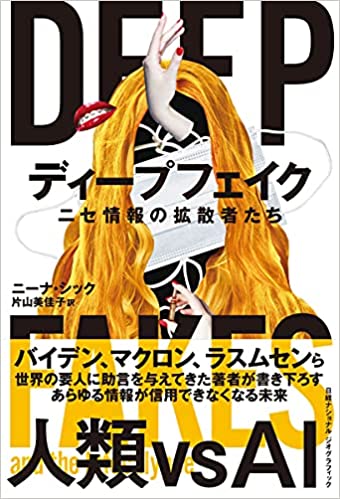 本と映画
本と映画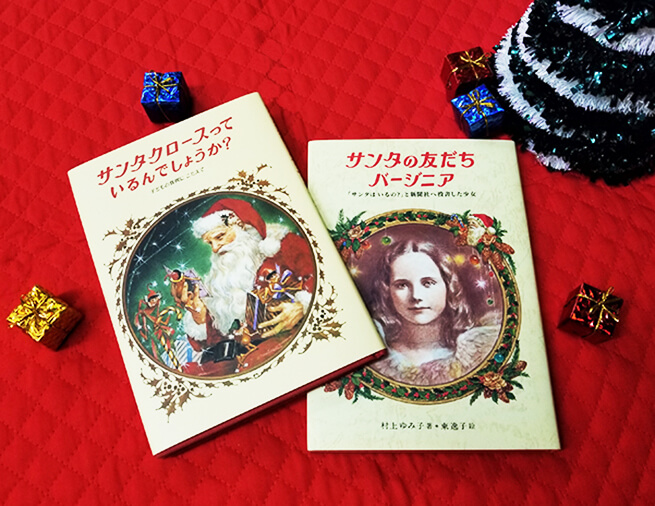 本と映画
本と映画 本と映画
本と映画 本と映画
本と映画 本と映画
本と映画