
小説を書くということは、非常に難しい作業なのだと思う。
とりわけ、自分の書いているものに対して徹底した客観の目を持ち続けねばならない、という点が。
熱い気持ちだけで書き進められるというものではないのである。
川上未映子の作品をきちんと読むのはこれが初めて。
メディアで見る彼女はきれいで魅力的だったし、思慮深い態度やその発言の内容にも好感を抱いていたので、
ときおりブログなどをのぞいたりしていた。
そこに書かれていることも非常にテンポが良くて面白く、才能のある人なんだなという印象を持っていた。
吉祥寺の本屋で平積みになった『ヘヴン』を手に取ったのは、夏の終わり。
白地に、大き目の明朝体のタイトルと著者名だけがある装丁がシンプルで美しかった。
まず第一に、タイトルがよい。ヘヴン!
おそらくタイトルが物語を引っぱっていったのではないか、とすら思うほど。
立ち読みで、最初の数行を読み、その後ページをめくってラストを読んだ。
泣けた。その場で泣いた。
それくらい最後の1ページ半の描写がよかったのだ。
場面の意味や事情は一切わからぬ。
けれどもそこには、臨界点に至った表現のかたちがあった。
それだけで一ぺんの珠玉の詩たり得るような、凄まじい密度が感じられた。
覚醒だ。
世界が「意味」を持つ以前の感覚が描かれているのだと思った。
それは、「涙ににじみながら目のまえにあらわれた世界はあらわれながら何度でも生まれつづけているようだった」
という一行にもっとも集約されていると思った。
(ここでは現象学や記号論などの解釈は持ち出さない。
あくまでも、斜視の手術をした後の(←あとで中身を読んで知った)主人公の個人的な体験が語られているのであるから。
物語に哲学的なあとづけをすることは、あまり意義のないことだと自分には思える)
また、
「僕は目をみひらき、渾身のちからをこめて目をひらき、そこに映るものはなにもかもが美しかった」
というようなやや破綻した文章の存在で、常軌を逸した感覚をひきたてることに成功している。
それから数ヶ月。
改めて本を開き最初から順に読みすすめ、昨日やっと読み終えたところ。
この作品は、いじめを受けている男子中学生の話なのだが、一言で言うと、川上氏はやはりあの最後のシーンを書きたくて長い物語を紡いだのだな、と思った。
この境地に至るまでに、登場人物と読者が経なければならぬプロセスが語られている、という印象なのだった。
(それくらいラストに力があるということなのだけれど)
丁寧に書かれているとは思う。
だが、物語の流れのいっさいが、おかしな言い方かもしれないが、物語じしんの想定する範囲内にきっちりと収まってしまっている。
あらゆる場面で既知感があるとも思った。
同様にいじめを受ける女生徒のコジマに誘われ、電車を乗り継いで彼が連れていかれた「ヘヴン」についても、ひっぱって期待させたわりにはありきたりでがっかりした。
90年代という時代設定だからそのくらいの刺激で丁度いいのかな、とも思うけど、それが作者のエクスキューズなのかなと読者に感じさせてしまっては意味がない。
(ついでに言うと、「俺そういうのって、無理」という台詞があるのだが、90年代には「無理」をそのようには使わなかったよね)
主人公がトイレで耳にした男子二人の意味ありげな会話や、放課後の教室での百瀬と女生徒の待ち合わせの場面など、こちらが何かの伏線だと読んでしまっていた出来事が結局展開されずに終わってしまったことも、残念だった。
散在したあらゆる事柄がベクトルとして一斉に最後のシーンに向かっていき、それらが気持ちよく収斂されていく、というものが、おそらく読者にとっての理想のかたちなのだと思う。
少なくとも、自分にとってはそうだ。
読書体験のカタルシスというのはそこにしかないと思うし、そうであってこそ、ヘヴンの美しさはさらに際立ち、唯一無二のものになるのだろうと思ったのだった。
スポンサードリンク:![]()
読んでくださってありがとうございます!
ポチッとしてね。






















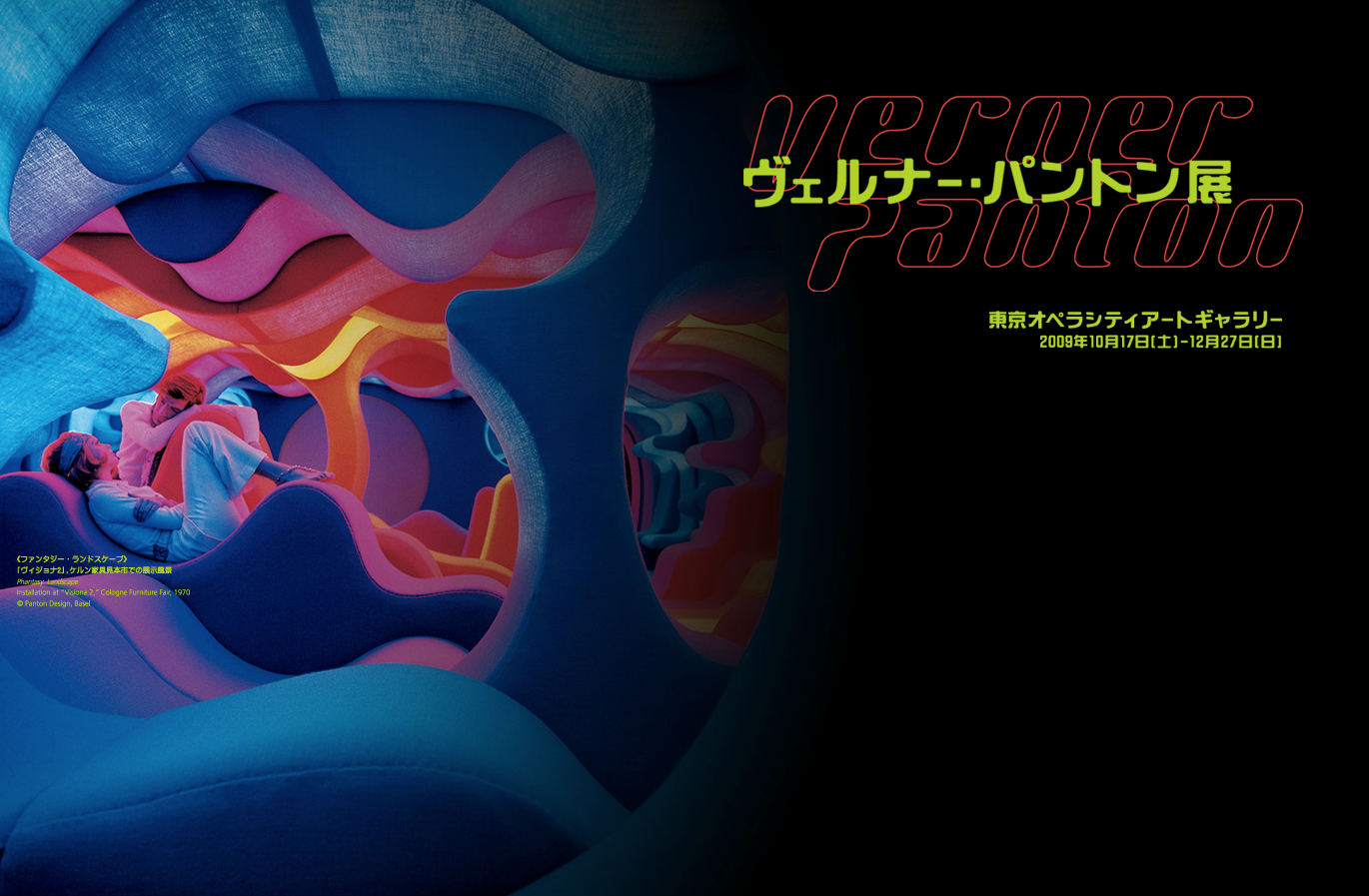
コメント