ご訪問いただきありがとうございます。
マンダラデザインアートブログのsachiです。
小池真理子氏の『月夜の森の梟(ふくろう)』を読みました。
2020年1月、肺腺がんで亡くなった作家の藤田宜永を、妻の小池真理子が回想したエッセイ。
ふたりは互いを「かたわれ」と思うような強く結ばれた関係だったという。
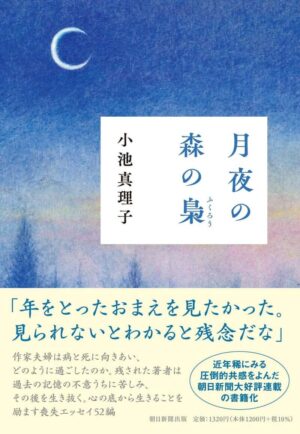
出典:https://bungeishunju.com/n/nb250ca171c51
(アイキャッチ画像にもお借りしました)
夫を見送った自分を描くということ
『月夜の森の梟』は、朝日新聞で連載されたものをまとめた一冊。
連載が始まったのは、藤田氏が亡くなって半年も経たない時期だった。
原稿依頼の打診があった時は放心状態で、まったく書ける状態ではないと返していたが、ある時、今しか書けないものを書き残しておこう、と思ったという。
以下は、文藝春秋digitalでの小池真理子談。
まだまともに仕事ができる状態ではなかったので、返事は保留にしてもらったんですけど、時間がたつにつれて、書いてもいいかなと思うようになりました。死別後2年、3年たって書くものと、直後に書くものは、たぶん全然違ってくる。言葉にならない思いを必死に紡ごうとする熱情みたいなものが、数年たつと少しずつ薄れて、よくも悪くも、まなざしが客観的、冷静になっていく。今しか書けないことがあるし、理屈では語りきれないものを言葉にすることで、自分を救えるかもしれない、という気持ちが強かったです。
出典:https://bungeishunju.com/n/nb250ca171c51
太字の部分、きっとその通りなのだろうと思う(太字は当ブログで装飾)。
「配偶者の死」という、ショッキングな出来事については特にそうだろう。
たいへんな作業だが、小説家ならやはり書こうと思うかもしれない。
ひとが経験する、ある意味普遍的なイベント(伴侶のいる人なら、いっせいのせ、で死なない限り誰もが経験すること)に当事者として臨んだとき、果たして自分の感情はどう動くのか?
それらをつぶさに観察し、丁寧に言葉に置き換えていく……。
過酷な作業だ。
以前投稿した展示会のことも思い出した。こちらはアート作品だが、失恋という一大事。

↑↑↑
「限局性激痛」とは医学用語で身体の狭い範囲を襲う鋭い痛みや苦しみを指す。
「人生最大の苦しみ」である自身の失恋体験をそう表現し、その痛みと治癒のプロセスを写真と文章で作品化した。
『月夜の森の梟(ふくろう)』 小池真理子著を読む
夕暮れ空のグラデーションに釣り針のように細い月が描かれた、美しい装丁の表紙を開く。
前書きは、「夫・藤田宜永の死に寄せて」。
その終わりの行は
それにしても、さびしい。ただ、ただ、さびしくて、言葉が見つからない。
とあった。
痛々しい。
そんな精神状態でどのように文章を綴っていくのだろう、、と心が痛む。
目次を見ると、静謐な印象の詩情豊かなタイトルが並ぶ。
梟が鳴く
哀しみがたまる場所
夜の爪切り
最後の晩餐
猫のしっぽ
金木犀
春風
繭にこもる
桜の咲くころまで
バード・セメタリー
かたわれ
などなど。
夫との出来事の記憶や、彼を亡くしたばかりの今感じることなどが、著者の住む豊かな森の季節の移り変わりとともに語られる。
自然描写と心象風景とが響き合い、そして溶けあうような、厳かな境地がどの掌編にも描かれていた。
(前書きの最後の行を読んで思ったようなことはまったく余計な心配!なのだった)
哀しみからの復活、再生の方法などわたしにはわからない、と著者は書く。
わからないこと、それ自体をここで書いてきたつもりだと。
心にしみるエピソードの数々
味わい深い掌編はいくつもあった。
<梟が鳴く>
ひとりで大きなどら焼きを食べていた時、夫が元気だったころ繰り返し言っていたことを思い出した。
それは、「俺が死んだ後のお前のことは想像できる、友達編集者相手に俺の思い出話をしながらおいおい泣いて、その割にはすごい食欲でぱくぱくまんじゅうを喰っているんだ」という軽口。それも、ひとつでは足りなくて2つも3つも、と言ったという。(読んでいて笑ってしまう)
そして、著者がどら焼きを手にそれを思い出し、おかしくてひとしきり笑いながら、気がつくと嗚咽していたというエピソード。
ユーモアもあるけれど、ほんと泣けてしまう。
<哀しみがたまる場所>
著者が慢性の肩こりで整形外科を受診。
理学療法士の若い女性は全身をチェックしたのち、左側の肋骨部分に触れ、ここにかなりの疲れがたまっている、と言う。
彼女は少しためらった後に、東洋医学では哀しみとか寂しさは肋骨の奥にたまると言われています、と言い添えた、と言うエピソード。
そうなのか。
こころがしんとなる。
医学だというのに、なんて詩的な表現なのだろうと思った。
ほかにも印象深いくだりがたくさんあった。
三十七年間、生活を共にしてきたが、百年も千年も一緒にいたような気がする。
〜<百年も千年も>より
どれほどの苦しみのさなかにあっても、人はふだん通りに生きようとする。これまでと変わらぬ日常を送ろうとする。私も同じだった。夫を見送った後も、起きる時間、食事の時間、寝る時間、すべて変えなかった。長年の習慣は、生きるよすがにもなる。
〜<音楽>より
そして書くことについて考えさせられた
心のうちと外で起こることを、それを表すのに一番ふさわしい言葉を選びながらきちんと表現することは本当に難しい。
この本を読んで思ったことは、その「言葉で表すこと」に対する真摯な姿勢こそが、人生に対する誠実さにつながるのではないか、ということ。
誰もが日々なんらかの文章を書いている。
軽々しい、上っ面だけの言葉をずらずらと並べて、出来事の周辺をなぞるばかりでは意味がない。
(このブログの文章がみごとにそれに該当する….. ; ; )
生きているうちに、血の通った、命の宿るような言葉をできるだけたくさん使いたいと思った。
小池真理子さん、ありがとうございます。
















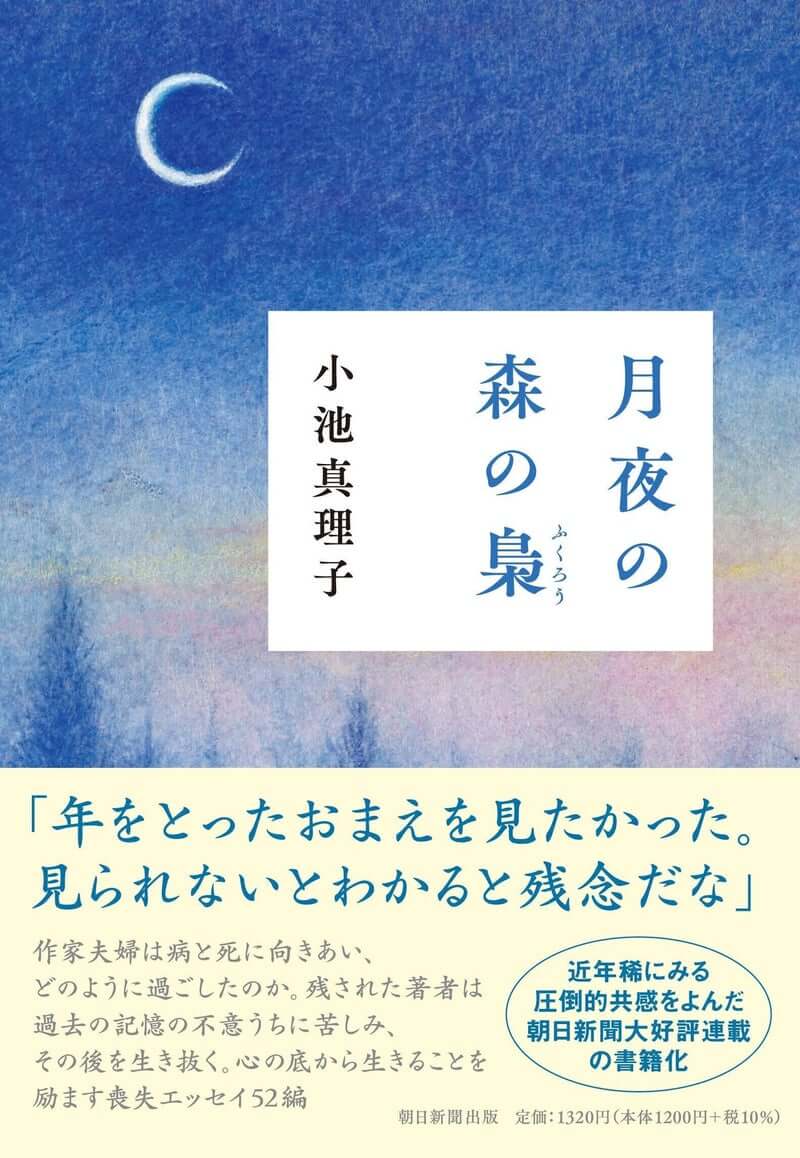








コメント